実は、こたぽん編集長はちょっと前にとある文献調査を行っていたんです。データは少し古めですが折角なので読んでみてください。
1 研究動機
最近ニュースなどでよく聞く「半導体」。その半導体をめぐって今、国家間で「戦争」が勃発しており、「半導体を制したものが世界を制する」と言われるほどヒートアップしている。そこで、半導体とは何なのか、そして今半導体をめぐって何が起きているのか、また、なぜ半導体が国家の命運を左右するのかを調べていこうと思った。
*本文で述べる「半導体」とは、半導体の性質を利用して作られた製品や半導体チップのことを指す。(2-1を除く)
2 半導体とは
そもそも半導体とはどのようなもので、どのような仕組みなのか。以下のようにまとめた。
2-1 半導体とは何か
半導体は、電気を通す「導体」の性質と、電気を通さない「絶縁体」の性質の中間の性質を持つ物質のことを言う。その物質は、外部からの衝撃や電気信号があった場合に電気が通り、その性質を利用してチップ状などに加工したものが、一般的に「半導体」と言われているのである。
2-2 半導体の仕組みとは
半導体の中には「論理ゲート」という論理演算⦅真の値(true:条件が成立)と偽の値(false:条件が成立しない)という、2つの値を用いて行う演算⦆を行う電子回路が入っている。論理ゲートにはいくつか種類があり、主に「AND」「OR」「NOT」「NAND」「NOR」の5種類である。
AND:2つある条件がともに「真」である場合のみ「真」を出力する演算のこと。
OR:2つある条件のいずれかが「真」である場合のみ「真」を出力する演算のこと。
NOT:1つの条件に対して、真偽値の値を反転させる演算のこと。
NAND:全ての条件がともに「真」である場合のみ「偽」を出力し、「偽」の条件がひとつでもある場合は「真」を出力する演算のこと。主にフラッシュメモリで使われている。
NOR:全ての条件がともに「偽」の場合のみ「真」を出力し、「真」の条件がひとつでもある場合は「偽」を出力する演算のこと。NANDと同じく主にフラッシュメモリで使われている。
今挙げたような論理ゲートがいくつも合わさって半導体チップが出来上がっている。
そのような論理演算を行う回路をプリントする基板となるのが「シリコン」だ。シリコンはケイ素の結晶であり、半導体に使われるシリコンは純度が99.999999999%(イレブンナイン)と、ほぼ不純物の入っていない超高純度となっている。初期の半導体ではゲルマニウムという別の物質が使用されていたが、ゲルマニウムは状態が不安定で非常に取り扱いが難しい。そのため、性質が安定していて取り扱いが簡単なシリコンが一般的に使われるようになった。
2-3 半導体略年史
半導体はどのようにして生まれ、どのような歴史を歩んできたのだろうか。
1945年 第2次世界大戦終戦
1946年 世界初のコンピューターが発表される
1948年 ウィリアム・ショックレー、ウォルター・ブラッテン、ジョン・バーディーンの3人(いずれも故人)が点接触型トランジスタを発明する
1955年 日本のソニーがトランジスタラジオを発売する
1957年 エサキダイオードが発明される
1959年 集積回路が発明される
1963年 電卓が発明される
1965年 ゴードン・ムーア(故人)が「ムーアの法則」を発表する
1967年 電卓が発明される・シャープが携帯型電卓を発売する
1968年 インテル社が設立される
1969年頃 電卓戦争が始まる
1970年 アメリカのインテルがDRAMを発売する
1971年 インテルによって「Intel 4004」が発売される
1972年 小型電卓「カシオミニ」の登場によって電卓戦争が終結する
1984年 日本人の技術者によってフラッシュメモリが発明される
1988年 インテルからフラッシュメモリが発売される
1989年 日の丸半導体(日本製の半導体のこと)が世界シェアの50%超を握る
2020年 日本のNTTが「光論理ゲート」の開発に成功する
2023年 日本の佐賀大学の研究チームが「ダイヤモンド半導体」の実験に成功する
2-4 半導体の種類
半導体にはどのような種類があり、それぞれにどのような役割があるのだろうか。
トランジスタ:半導体の中でもっとも私たちの生活にかかわりのあるものが「トランジスタ」である。トランジスタは「電気の流れを制御する部品」で、 電気信号を大きくする増幅機能と、電気を流したり止めたりするスイッチング機能がある。今ではほぼすべての電子機器に使用されており、無くてはならない部品となっている。
ダイオード:ダイオードは、電気の流れを一方通行にする電子部品である。 ダイオードは半導体を用いた基本的な部品で、電気の流れを整えたり、電圧を一定にしたり、検波したりできる。発光ダイオード(LED)はダイオードが発光したものである。
メモリ:恐らく最もよく聞く単語であろう「メモリ」。簡単に言えば「記憶装置」である。実はこれには「DRAM」、「NAND」、「NOR」の3種類がある。DRAMは短期記憶に適しており、電源を切るとすべてのデータが消去される。主にパーソナルコンピューターやスマートフォンに利用されている。それに対してNANDは長期記憶に適しており、電源を切ってもデータが消去されることはない。DRAMと同じく主にパーソナルコンピューターやスマートフォンに利用されている。NORはNANDと比べて書き込み速度や集積度(半導体集積回路一個当たりに組み込まれた素子の数)において劣るものの、読み込み速度は速く、Wifiルーターやプリンター、デジタルカメラなどに利用されている。
DRAMとNAND、NORは「フラッシュメモリ」と呼ばれることが多い。フラッシュメモリは東芝社員(当時)の舛岡富士雄氏が発明し、インテルが発売した。
フラッシュメモリーをめぐっては、2004年に舛岡氏が東芝から十分な研究報酬金を受け取っていなかったとして11億円の支払いを求め東芝に対して民事裁判を起こした。この裁判は2006年に東芝が舛岡氏に8700万円を支払うことで和解が成立している。
ロジック半導体:ロジック半導体は簡単に言うと「電子機器の頭脳」である。これがなければ電子機器は動かない。主にスマートフォンやパーソナルコンピューターに中央演算処理装置(CPU)として搭載されている。
パワー半導体:パワー半導体は簡単に言うと「電子機器の筋肉」である。主に大きな電流や電力を扱うことを目的として製造されたもののことを指す。主に洗濯機や掃除機、炊飯器などに搭載されている。
アナログ半導体:アナログ半導体を簡単に言うと「電子機器の触覚」である。光や音などの物理的な現象の変化に対する連続的な電気信号処理・制御するための半導体として利用されている。この半導体はセンサーで取り込んだ光や熱(温度)、音声、振動などのアナログ信号をデジタル信号に変換したり、またその逆を行う。スマートフォンやIoT機器、自動車などに幅広く使われている。
イメージセンサー:イメージセンサーを簡単に言うと「電子機器の目」である。レンズから入った光を電気信号に変換する役割を負う。現在では「CMOS」という方法が主流となっている。多方式と比較しても安価で小型化技術も進んでいることから、現在ではほとんどの電子機器でCMOSイメージセンサーが採用されている(携帯電話・小型カメラなど)。日本のソニーが圧倒的なシェアを占める。
2-5 半導体ができるまで
半導体の製造工程は以下のとおりである。
| 製造工程 | 説明 | この分野で世界シェア1位を握る日本企業(装置) | この分野で世界シェア1位を握る日本企業(材料) |
| 前工程 | |||
ウエハー製造 | 高純度のシリコンから半導体の土台となる円形の薄い板(ウエハー)を作る | なし | 信越化学工業SUMCO |
成膜 | ウエハー上に回路の素材になる薄い酸化膜。窒化膜を形成する | なし | なし |
レジスト塗布 | 紫外線に反応する薬液を塗布する | 東京エレクトロン | JSR東京応化工業信越化学工業住友化学富士フィルム |
フォトマスク製造 | 回路パターンを転写するためのネガを製造する | レーザーテック(検査装置) | HOYA(マスクブランクス) |
露光 | 回路パターンを描いたフォトマスクをウエハーに合わせ、UV光を照射してパターンを転写する | なし | なし |
エッチング | フォトレジスト*上に現像されたパターンに沿って成膜された酸化膜、窒化膜を取り除く | なし | なし |
洗浄 | 不要になったフォトレジストを取り除く | SCREEN HD | なし |
平坦化 | 回路上の凸凹をなくし、平坦にする。 | なし | なし |
ウエハー検査 | ウエハー上に完成した回路一つ一つに検査針を当てて不良品をはじき出す。 | 東京精密 | なし |
| 後工程 | |||
ダイシング | ウエハーをチップごとに切り分ける | ディスコ | なし |
| パッケージングテスト | チップを樹脂で包み、機能を検査する | アドバンテスト | なし |
レジスト塗布では、製造装置・材料共に日本勢が世界シェア90%以上を占める。いまだに半導体製造工程では日本企業が強いことがうかがえる。
*フォトレジストは、半導体製造において欠かせない化学薬品で、電子回路を形成する役割と、電子回路を形成して欲しくない部分を保護する役割がある。
3 半導体業界に今何が起きているのか
日米蘭が先端半導体及び製造装置の対中輸出規制で合意した―2022年10月、この一報に半導体関係者には衝撃が走った。日本の対中輸出品目の大部分を半導体製造装置が占めているのに、なぜ対中輸出規制に踏み切ったのか、と。背景には「アメリカの戦略」がある。その「戦略」とは何なのだろうか。
今回の対中輸出規制の背景には、半導体の「安全保障上の半導体の重要性」が強く影響してくる。今や半導体は日常生活ではもちろんのこと、最先端の武器を製造するうえでも重要になっている。そんな半導体業界で今、中国が存在感を放っている。「このまま中国を野放しにしておいたらアメリカの軍事的優位性が崩れてしまう」。こんな危機感を持ったアメリカが決断したのが「半導体製造装置の禁輸」である。
今回の輸出規制のポイントは主に5つある。
1.中国のスーパーコンピューター(スパコン)やAIに使われる高性能半導体の輸出を禁止する。その対象には、アメリカ国内外でアメリカの設計技術や装置を使って製造された高性能半導体が含まれる。(注2)
2.アメリカ製の製造装置の中国への輸出を禁止し、アメリカ人が関わることを禁止する。(注2)
→この条文によって既存のアメリカ製の装置のメンテナンスが一切できなくなった。
3.規制に該当する成膜装置を輸出する場合、アメリカ政府の許可を得なければならない。先端半導体メーカー向けか、非先端半導体メーカー向けかは関係ない。(注2)
4.中国の半導体製造装置メーカーに、アメリカ製の部品や材料を輸出することを禁止する。そのメーカーが製造する装置が、先端半導体向けかどうかは一切関係ない。(注2)
5.中国にある外資系メーカーにも規制を適用する。(注2)
→この条文は海外企業にも影響を及ぼすと予測されている。
以下に戦略の具体的な内容を示していく。
前工程(詳細は2-5を参照)では、主要な工程の製造装置において、日米蘭のメーカーが各分野でシェアを独占しているが、このような中で、今回の輸出規制は中国の半導体産業にどのような影響を与えるのだろうか。
まず、中国先端半導体メーカーおよびTSMC、サムスン、SKハイニックスは工場の新増設が不可能となる。先端でなければ可能かというと、そうではない。なぜなら先端半導体メーカーに対しては、非先端半導体メーカー向けの装置の輸出も禁止されているからだ。オフィス家具もダメという徹底ぶりである。
次に、半導体成膜装置を輸出する際は、アメリカ政府の許可を得なければならないという記述がある(輸出規制ポイント3)。この項目では成膜の材料からプロセス(工程)条件、膜の厚さに至るまで詳細なところが規定されている。ところで、なぜアメリカ政府は成膜装置に規制をかけたのか。半導体の製造はシリコンウエハーに薄膜を付けるところから始まる。その後も様々な工程で薄膜を付けていく。あらゆる半導体の製造には成膜過程が必要不可欠なのである。成膜しなければ、その後の微細化加工ができない。成膜装置に規制をかけたということは、半導体製造の急所中の急所を抑えたということになる。
この規制の効果はいつか中国の手によって破壊されるだろう。しかし、効果が出ているうちに日米蘭が更に先端半導体の開発を進めていくことで、効果が無くなっても中国を技術面で引き離すことができる。今後の日米蘭の先端半導体の開発のスピードも規制の効果に大きく関わってきそうだ。
日米蘭のこの厳しい輸出規制に、流石の中国も黙ってはいなかった。中国政府は2023年8月1日からこの対中輸出規制への「報復」ともいえる措置を適用する。この報復措置の内容は「ガリウムやゲルマニウム、窒化ガリウムの日米への輸出を規制する」というものだ。
ガリウムは未来半導体開発や有機ELディスプレイ素材などとして使われており、またゲルマニウムは、半導体工程用ガス生産などに使われる。これらの半分以上を中国が生産している。これらのものは既に多くの分野で利用されており、日本企業への影響も大きい。早急な代替確保先を確保する必要がある。
窒化ガリウムはシリコンと比べて電力損失が少なく、次世代半導体や5G端末への利用などが進んでいて、需要増が期待されている。窒化ガリウムはまだ各社が研究を始めた段階であり、今回の報復措置による日本企業への短期的な影響は限定的とみられている。ただ、中長期的に見れば日本企業は一定程度の打撃を受けることになるかもしれない。
日米蘭VS中国のバトルを見ただけでも既にデスマッチが激化していると言えるだろう。
4 日本と半導体
4-1 圧倒と凋落
「アメリカの半導体産業は終わった」誰もがそう感じた時があった。1980年代後半、日本が世界の半導体シェアの過半数を握ったのだ。
その理由は日本の半導体メーカーが受けていた「政府からの補助金」にあった。半導体の開発には巨額の資金が必要である。しかし政府から巨額の資金支援を受けることでその費用を安く抑え、製品の品質を高く保つことができ、日本企業に莫大な利益をもたらした。また、当時の日本の金利は低く、企業はいくらでも銀行から融資を受ける(お金を借りる)ことができた。そう、いくらでも資金が沸いて出てくるのだ。このような日本企業にとって好条件の下、日本の半導体企業はどんどん飛躍していった。
アメリカのある科学者の報告によると、3社の日本企業のうち、最初の1000時間の使用で故障率が0.02%を上回った企業は一つもなかった。対して、3社のアメリカ企業の故障率は最低でも0.09%。なんとアメリカ製の半導体のほうが4.5倍も故障が多いということになる。(注1)つまりアメリカ企業の作る半導体の品質は、競合企業である日本企業よりも極端に悪かったのである。性能は同じ、価格も同じ、でも品質は悪い。そんな商品をいったい誰が買うというのだろうか。半導体産業のみならず自動車産業から製鉄産業まで、全てのアメリカ企業が、この日本企業との熾烈な競争にさらされ、負けていった。一部の企業を除いては。
1978年、アメリカのアイダホ州で一つのメモリーチップメーカーが産声を上げた。「マイクロン・テクノロジー」である。マイクロンは「ミスタージャガイモ」ことジャック・R・シンプロットが支援し、徹底的なコスト削減に努めた。当時、日本企業はその独占的な地位を利用してDRAMを高価格で販売していた。それによって大きな利益を上げていたのだ。マイクロンは生産コストを削減し、高品質な製品を安価で売ることで競合する日本企業を追い落としていった。「コスト面で競合する企業に勝つ」、これこそがマイクロンの戦略である。
コスト面でアメリカに負けた日本。しかし、この後更なる大反撃に見舞われる。1986年、アメリカ政府が「アメリカの安全保障を脅かす」として、「日本政府は日本国内の顧客に対してアメリカ製半導体の活用を奨励すること」など、アメリカ側に有利な条件を盛り込んだ日米半導体協定の締結を日本に強要させた。その翌年にはレーガン大統領(当時)が「アメリカ製の半導体の割合が達成されていない」などとして、日本の電子製品に100%の超高関税をかけて圧力を強めた。そして1991年に協定が満期を迎えると、新たに「日本国内で生産する半導体規格をアメリカの規格に合わせること」や、「日本市場でのアメリカ半導体のシェアを20%まで引き上げること」を要求し、第2次協定の締結を強要した。そして第2次協定が満期を迎えた1997年、アメリカは日本の半導体産業の勢いが失われたことを確認すると、ようやく協定の失効を認めた。このころには、日本の半導体産業はもうすでに時代遅れと化していた。他にもDRAM市場の不況や景気の落ち込み、アメリカの金利が日本の金利を下回ったことなど様々な要因があり、それらが重なり合ったことで日本企業に大打撃を与えたのである。
アメリカの圧力などによって日本の半導体産業が衰退していく間に急成長したのが韓国である。アメリカは「敵の敵は友」という有名な理屈を利用して韓国政府への支援を開始。その恩恵をあやかり大成功したのが今でも業界で首位を走るサムスン電子である。
こうして日本の半導体産業はあっという間に凋落していったのである。しかし今、再び日本の半導体産業を盛り上げようという動きが加速している。
4-2 復活へ
日本は半導体協定のトラウマから、長年アメリカの顔色をうかがいながら半導体を製造していた。その間に、中国や韓国の企業は政府の手厚い支援を受けて半導体産業を発達させてきた。それによって日本の半導体産業はほぼ完全にシェアを失った。
そのような中で復活に向けた動きは着々と進んでいる。2019〜2020年にかけて、NTTが世界を驚愕させる技術を次々と発表した。「光トランジスタ」「全光スイッチ」「光論理ゲート」(光電融合技術)である。光は電気よりも大容量で早くデータを送ることができる。そのため、半導体の3次元化及び情報処理の高速化などに大きな影響を及ぼすといわれている。光トランジスタは、電気信号を光信号に、光信号を電気信号に変換し、入力した光信号を別の光に変換・増幅する素子のことをいう。全光スイッチとは、光信号のオン/オフや光の行き先を切り替える。光論理ゲートは超高速の演算処理を担う素子のことをいう。NTTは2030年までにこの光電融合技術を使った何らかの製品を発表するとしている。そして早速NTTが動き出した。NECに出資し、富士通と資本提携を結んだのである。通信業者がモノづくりの領域に降りていく・・・誰もが驚いたはずである。そしてグループの稼ぎ頭であるNTTドコモを完全子会社化し、収益の基盤を強化した。この技術はとてつもなく大きな可能性を秘めており、実用化されれば日本の軍備(=国家機密)や家電製品などに使用されることとなるだろう。その時に日本独自の技術を使った半導体を海外で製造していてはその国に国家機密が筒抜けとなってしまう可能性がある。それを防ぐためには、日本国内に工場を置く必要があるため、国内に工場を持つ富士通と資本提携を結んだのである。今のところ、この技術を使った製品を製造することができるのはNTTのみである。日本が世界を揺り動かすことはできるのか。しかしこれを実現するためには、何兆円とかかるであろう開発資金を調達し、インターネットの始祖であるアメリカの協力を取り付けなければならない。その先にあるのは技術をめぐる国際政治の荒波である。まだまだ道のりは長い。
2022年10月、世界最大手の半導体製造メーカーのTSMCが熊本県に工場を建設すると発表した。世界最大の半導体製造メーカーを日本に誘致することで技術者などの育成に役立つことが予想され、日本の半導体産業の復活へ向けた大きな一歩となるだろう。
2022年11月、国策会社「Rapidus(ラピダス)」が設立された。Rapidusはトヨタなど日本の主要8企業の共同出資によって設立された。RapidusはIBMとの提携を発表し、大量生産技術の確立していない2ナノメートルの製品の製造技術をライセンス購入することとなった。TSMCの後を追う形で2027年の先端半導体の量産を目指す。また、この半導体を製造する工場を北海道に建設することを発表し、政府が2600億円という巨額の補助金を支出することも発表した。これによってRapidusは日本の主要企業と政府の双方からの支援を取り付けた形となり、研究開発が一層進むと考えられるのではないだろうか。
2023年4月、佐賀大学の研究室が世界初となるダイヤモンド半導体の実験に成功したと発表した。研究チームによると、高速スイッチング動作と長時間連続動作が可能なことを確認したそうだ。ダイヤモンドは、シリコンなどほかの素材と比べて熱伝導率が高く放熱性に優れている。また、高寿命で大きな電力でも制御することができ、世界中から脚光を浴びている。研究チームは2026年の実用化を目指すとしている。これが実用化されれば世界は大きく変わることとなる。元々ダイヤモンド半導体の開発は日本が世界をリードしてきたが、今回の発表によって改めて日本のリードが確固たるものになったといえるだろう。しかし、これには課題もある。それは「大企業を巻き込めるか」だ。現在はまだ開発に成功したに過ぎず、これから実用化に向けていかに量産していくかが課題となってくる。高品質の製品を量産するには日本の大企業の協力が欠かせない。今後、いかに佐賀大学が大企業を巻き込めるのかが今後重要となってきそうだ。
同年7月、経済産業省が工業用水の新規整備への補助金交付を再開した。半導体は少しの埃や塵が付着しているだけで性能が大きく損なわれるため、それを洗浄するためには、限りなく純水に近い濃度の水(理論純水が最も望ましい)が大量に必要である。現在の日本の工業用水は多くが老朽化しており、ほとんどの自治体にそれを補修する財力は残っていない。そのような状況の中、日本各地に半導体工場が続々と新設されており、工業用水網の整備は大きな課題となっていた。この補助金交付の再開でその課題が解決されたことで、より一層復活への動きが加速するはずだ。
以上が日本の復活への動きである。これらの企業及び日本政府の今後の支援の動向が日本の運命を左右することとなり、そこが今後の大きな焦点となっていくのではないだろうか。
4-3 復活への課題
ただ、復活への課題もある。
一つ目の課題は「人手不足」である。今、TSMCの熊本誘致を皮切りに日本全国に続々と半導体製造工場が建設されているが、半導体製造工場で勤務する人手が不足している。現在日本では少子高齢化による人口減少が大きな課題となっており、それが大幅な人員不足を招いている(TSMC熊本工場では毎日1000人程度が足りなくなるという試算もあるほどだ)。また、この約30年の間に多くの優秀な技術者たちが中国や韓国などの海外に渡ってしまったり、そもそも技術者自体が減ってしまっている。そのため、若くて優秀な人材の早急な発掘・育成も重要となってくる。
二つ目の課題は「本当にRapidusが半導体を量産することができるのか」である。2001〜2002年にかけて日本政府は国策半導体プロジェクトとして「みらい」「はるか」「あすか」「あすかⅡ」「AS☆PLA」「DIIN」を巨額の国費を投入して進めてきた。しかし、いずれのプロジェクトも大した成果を上げることができないまま2011年までに全て解散(失敗)している。そのため、巨額の国費が投入されて発足した「Rapidus」が本当に国産先端半導体を量産することができるのか、という不安があるのも事実である。今後Rapidusはどのようにして国産先端半導体を量産するのか、それとも過去の国策プロジェクトと同じように破滅の道を歩むのか、今後の動向を注視していきたい。
このように、日本が半導体復権を目指す上での課題は大きく分けて二つある。この二つの問題を解決してもまだまだ課題はたくさん出てくるであろう。だが、日本は過去に数々の難局を乗り越え、経済的に大きく発展してきたのだから、きっと「半導体の失われた30年間」も乗り越えることができるはずだ。
5 なぜ半導体が国家の命運を左右するのか
では、なぜ半導体は国家の命運を左右するといわれているのだろうか。生活面と軍事面から考察する。
〈生活面〉
まず、生活面から見ていく。今この瞬間に世界から全ての半導体が消し去られたとしよう。すると何が起こるのか。当然のごとくパソコン、スマートフォン、タブレットは使えなくなる。他にもエアコン、炊飯器、テレビ、ラジオ、自動車などありとあらゆるものが一瞬として動かなくなり、ただの塊となる。
今挙げた物では、どのような部分で半導体が利用されているのだろうか。パソコンやスマートフォンのOS(オペレーティングシステム:WindowsやMacなど)やアプリなどを正常に機能させたり、インターネットに接続させたりするところなどで半導体が利用されている。エアコンにはリモコンからの電波を受信したり、風量や温度を一定に保つための部分などに半導体が利用されている。炊飯器は、米を炊く時の方法を記憶させ、それを実行させる部分などに使用されている。自動車ではカーナビで現在地を把握したり、「走る」「曲がる」「止まる」など基本的動作を制御する部分などに使用されている。これらの物は、半導体が一つでもなくなったら動くことができない。
逆に半導体が使われていない物は、机、椅子、本棚、紙、鉛筆などが挙げられる。しかし、これらの物は、半導体によって自動化された製造装置によって生産されているため、製造が困難になるだろう。これらの物は頑張れば自分でも作ることができるかもしれないが、これらを作るには工具が必要だ。その工具も半導体を用いた装置によって製造されている。最悪これらの物は自分で鉄鉱石を溶かして作れば製造することが可能ではあるが、この自動化社会に慣れ切った私たちでは、ほぼ不可能であろう。
つまり、半導体が無くなったら私たちの便利で快適な生活は一瞬で崩壊するということだ。そして今、世界では実際にこのようなことが起こるかもしれない。その引き金となり得るのが台湾侵攻だ。
実は、台湾侵攻によって半導体の製造が止まった場合の、世界への影響を示したデータがある。CIAの長官が5月上旬の公聴会で発言した「中国による台湾侵攻で半導体生産が止まれば、年間約130兆円の経済損失が発生する」という試算である。仮にそうなったとすれば世界経済に大打撃を与え、製造業はもちろんのこと、他の業種にもその影響は広がるだろう。またその状況が長く続いた場合、上記のようなことが起こる可能性が高くなる。そのようなことを防ぐために、TSMCは今「保険」として、日本やアメリカ、シンガポールなどに半導体工場を建設している。そのうちのアメリカ工場では、最先端の5nm(ナノメートル)半導体を製造する予定だ。TSMCの工場は今、「世界展開」しようとしているのである。しかし、このような台湾侵攻という最悪の事態に陥らないようにするためにも、如何にして中国の台湾侵攻を阻止するかが、アメリカや日本に求められている。
〈軍事面〉
次に、軍事面から見ていく。最先端の軍備を開発・製造するには最先端の半導体が必要である。なぜなら、そうしないと的確に敵を狙うことができないからだ。的確に敵を狙うことができるということは、それだけ命中率が上がるということである。そうすれば最小限の弾薬で敵を壊滅状態に追い込み、勝利を収めることが可能となる。それを最大限活用し、世界で軍事的な優位に立つことができているのがアメリカと中国である。軍事的に優位な立場に立つということは、その国がその地域の覇権を握るということになる。軍事力が強ければ他国との戦争で勝利することができ、それによってその国が国際社会の中で無視できない存在となり、結果として世界の覇権を握ることにもつながるからだ。それを体現したのがまさにアメリカである。アメリカはその軍事力を生かして第1次世界大戦、第2次世界大戦など数々の戦争で勝利をおさめ、世界の覇権を握っているからである。その国の軍事力、そしてその地域での軍事的優位性に直結する半導体は、やはり重要であるといえるだろう。
現在、色々な場面で「半導体は21世紀の石油である」とよく言われているが、その言葉からも半導体の重要性がうかがえる。石油は戦車や航空機、艦船を動かす燃料であり、20世紀、石油で覇権を握ったものは世界で大きな影響力を持つことができた。しかし今、半導体は石油以上に重要な戦略物資となっている。デジタル化が急速に進む世の中では、今や半導体がなければ何もできない。自らの世界を広げてくれるインターネットも、人々の交流の場となっているSNSもそうである。21世紀の現代で動いているほぼすべてのサービスは半導体がなければ機能しないのだ。そして全ての軍備も、今や半導体なしでは動かない。旧世代の軍備は半導体がなくても何とか動くが、最新の軍備は特にその影響を受けやすい。そのため、海外製の半導体に頼っていると、有事の際に輸入が止まった場合、自軍は兵器を消耗するだけで勝ち目が無くなる。有事の際に持ちこたえるには、自国で半導体を生産する能力を持つことが極めて重要なのである。つまり、半導体は「有事の際に国家が生き残れるか」を決定づけるものと化したのである。それゆえに、「国家の命運」を賭けた「デスマッチ」となっているのである。
6 結論
今、半導体は石油以上に重要な戦略物資と化しており、その製造能力をめぐって激しい競争が起きているということが分かった。現在の半導体覇権国であるアメリカは、急速に台頭する中国の半導体産業を壊滅させるために、日本やオランダと協力して対中輸出規制を実施している。ただ、その効果は中国の努力によっていつ破られるか分からず、どうすれば効果が出ているうちに技術面で中国を引き離せるのかが、日米蘭に求められている。
私たちの生活から半導体が無くなったら、私たちの便利で快適な生活は一瞬で崩壊し、大混乱に陥ってしまう。また、半導体は現代の軍事作戦にも必要不可欠であり、半導体がなければ現代の最新兵器は全て無力となるのである。半導体の供給を他国に依存していると、仮に有事が発生して半導体の供給が停止した場合に、その国は高性能な軍事兵器を新しく製造することができなくなってしまう。如何にして半導体の製造能力を構築するのかということも、国家にとって大変重要なのである。それほど現在半導体の重要性が高まっており、更には半導体の製造能力が国家の命運まで左右してしまうのである。
現在、日本は半導体の多くを国外に依存しているが、今後国内で安定して半導体を製造することができるよう、日々たくさんの努力をしているのだと思った。半導体は私たちの日常生活に大きな恩恵をもたらしているが、その製造能力をめぐるデスマッチの結果が、各国の命運を左右することにつながると言えるのだ。これからデジタル化が進むにあたって、更に半導体の製造能力をめぐって激しい競争が繰り広げられていくと予想されるが、その結果が、破滅ではなく私たちの日常生活に更なる恩恵をもたらしてくれることを願いたい。今この機会を逃したら、日本の半導体産業の復活への道は絶たれてしまうのではないか。そのような危機感のもと、日本は今、世界で各国間の半導体をめぐるデスマッチがますます激化する中での、日本の半導体産業の復活という大きな目標を達成しようとしている。しかし、その大きな目標の前には「世界中で若手技術者の争奪戦が繰り広げられている中で、優秀な若手技術者を獲得することができるのか」、「巨額の国費を投入して設立されたRapidusは本当に国産の先端半導体を量産できるのか」などといった、沢山の壁が立ちはだかっている。このラストチャンスを逃さないためにも、これらの課題を官民共同で一つずつ解決していき、日本の半導体産業復活に向けた取り組みを進めていくことが重要なのではないだろうか。
参考文献
出典
書籍(発行年、五十音順)
・漢字源 改訂第5版(学研教育出版、1988年)
・三省堂 現代国語辞典(三省堂、1990年)
・NHKスペシャル新・電子立国1~6巻(相田洋・大墻敦・荒井岳夫・矢吹寿秀・赤木昭夫 著、日本放送出版協会、1996年~1997年)
・現代用語の基礎知識 学習版 2020-2021(自由国民社、2020年)
・週刊東洋経済「半導体狂騒曲 黒子から主役へ」(東洋経済新報社、2020年)
・図解入門業界研究最新半導体業界の動向とカラクリがよ~くわかる本[第3版](センス・アンド・フォース 著、秀和システム、2021年)
・「半導体」のことが一冊でまるごとわかる(ベレ出版、2021年)
・2030半導体の地政学 戦略物資を支配するのは誰か(太田泰彦 著、日本経済新聞出版、2021 年)
・三省堂国語辞典 第八版(三省堂、2022年)
・週刊東洋経済「半導体 次なる絶頂」(東洋経済新報社、2022年)
・週刊ダイヤモンド「半導体 最後の賭け」(ダイヤモンド社、2023年)
・半導体産業のすべて 世界の先端企業から日本メーカーの展望まで(菊池正典 著、ダイヤモンド社、2023年)
・半導体戦争 世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防(クリス・ミラー 著 千葉敏生訳、ダイヤモンド社、2023年)
・半導体有事(湯之上隆 著、文藝春秋、2023年)
・半導体立国ニッポンの逆襲 2030復活シナリオ(久保田龍之介 著、日経BP、2023年)
・ニュースがわかる特別ムック 半導体がわかる(毎日出版、2023年)
ウェブサイト
・一般社団法人 電子情報技術産業協会 半導体部会(最終閲覧日2023.02.20)
・東京エレクトロン(最終閲覧日2023.02.20)
・半導体株調査部 半導体株の分析と投資実践(最終閲覧日2023.02.20)
・TECHブログ(最終閲覧日2023.02.20)
・日経XTECH(最終閲覧日2023.02.20)
・経済産業省(最終閲覧日2023.04.02)
・ITを分かりやすく解説(最終閲覧日2023.04.16)
・Wikipedia(最終閲覧日2023.08.12)
・ニューズウィーク(最終閲覧日2023.04.22)
・FEDERAL REGISTER(最終閲覧日2023.05.13)
・Breau of Industry and Security(最終閲覧日2023.05.13)
・Code of Federal Regulations(最終閲覧日2023.05.13)
・Inveator(最終閲覧日2023.05.13)
・NHK NEWS WEB(最終閲覧日2023.05.13)
・Google翻訳(最終閲覧日2023.06.02)
・コトバンク(最終閲覧日2023.08.13)
その他
・NHKスペシャル 電子立国日本の自叙伝(NHK、1991年)
・NHKスペシャル 半導体大競争時代(NHK、2023年)
・日本経済新聞(日本経済新聞社、2023.01~2023.07)
・朝日新聞(朝日新聞社、2023.07)
・Bing AI(Microsoft、最終質問日2023.07.29)
*Bing AIは本研究で使用した海外文献の翻訳や文章の要約に使用しており、調査・考察には使用していません。
引用
注1(本文5頁35~37行):クリス・ミラー 著 千葉敏生 訳「半導体戦争」ダイヤモンド社、2023年、124頁2~4行目
注2(本文4頁25~28・30~34行):湯之上隆 著「半導体有事」文藝春秋、2023年、26頁11行~27頁12行の随所
*この文章の情報は2023年7月31日時点のものです。
以上が編集長が2023年に書いた研究レポートでした。当時と違い生成系AIブームで台頭したNVIDIAなどについては触れられていませんが、現在の状況と見比べてみると興味深いものがあります。皆さんはどうでしたか?ちなみに編集長は理系じゃありません。文系です。

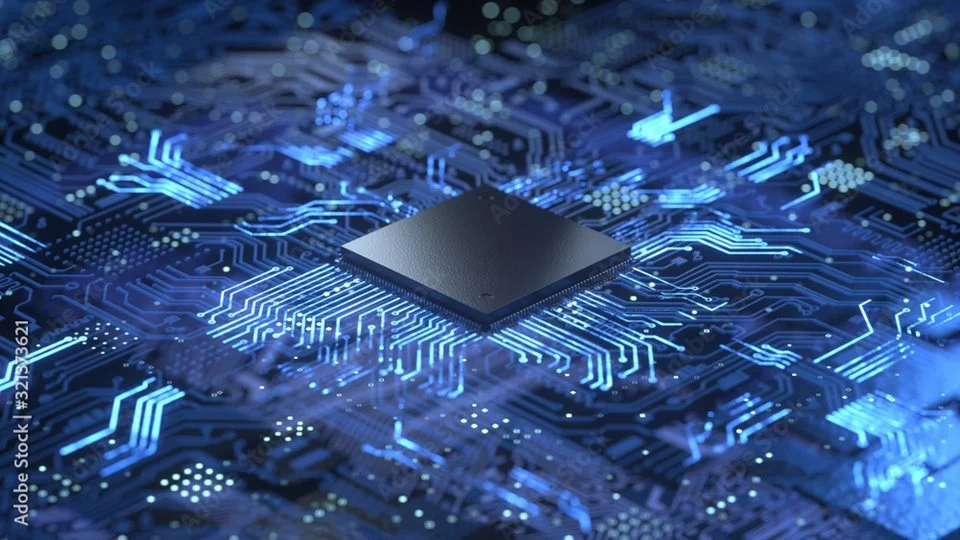


コメント